ジーザス、エブリワン!キートンです。

分かりやすく教えて!
こういった疑問にお答えします。
キリスト教は、1人の神様を信じる一神教です。
しかし、キリスト教にはこの世界を造られた神様の他に、イエスキリストという神的存在もいます。
そうなると、神様が2人になってしまい、

と首をかしげたくなるかもしれませんが、実は矛盾していません。
なぜなら、キリスト教には、“三位一体(さんみいったい)”という重要な考え方があるからです。
これは、政治などで使われる三位一体とは違います!
しかし、三位一体はキリスト教の中でも最も理解が難しい概念の1つであり、きちんと理解している方は少ないでしょう。
そこで今回は、クリスチャンの僕が、
- 三位一体とは?わかりやすく簡単にクリスチャンが解説【キリスト教】
- 三位一体の位格をそれぞれ解説
- 三位一体説はどのようにして生まれた?【2つの会議で成立】
- 日本では昔”三位一体の改革”が行われた?
などについてわかりやすく解説します!

👇動画で見たい方はこちら
目次
三位一体とは?わかりやすく簡単にクリスチャンが解説【キリスト教】

三位一体というのは、神様は3つの位格を持っておられるという考え方のことです。
位格というのは、人間で言うと人格のようなものですね。
そして、その3つの位格というのが
です。
それぞれの位格に上下関係はありませんが、役割分担があります。
ここだけ聞くと、

やっぱり矛盾してる!
と思うかもしれませんが、矛盾はしません!
なぜなら、三位一体というのは神様が3つ合わさって1つなのではなく、
1つの神様の中に3つの位格があるという考え方だからです。
どの位格も本質は同じであり、実体としては1つ。
ですから、神様はあくまでも1人だけなんですね。

これはキリスト教において非常に重要な考え方で、三位一体を認めない宗派は異端とされているほど。
実際、三大宗派(カトリック、プロテスタント、正教会)を含めたキリスト教の多くの宗派がこの教えを受け入れています
✅キリスト教の主な宗派については、【解説】キリスト教の主な宗派は?3つをわかりやすくまとめてみたをどうぞ
三位一体の位格をそれぞれ解説
それでは、神様のそれぞれの位格を見てみましょう。
- 父なる神(創造主)
- 子なる神(イエス・キリスト)
- 御霊なる神(聖霊)
①父なる神(創造主)

この世界や生物たちを造られた、全知全能の神。
旧約聖書の創世記には、創造主による“天地創造”の様子が描かれていますね。
「こうして天と地と、その万象とが完成した。 2神は第七日にその作業を終えられた。すなわち、そのすべての作業を終って第七日に休まれた。 3神はその第七日を祝福して、これを聖別された。神がこの日に、そのすべての創造のわざを終って休まれたからである。 4これが天地創造の由来である。」
(創世記2章1~4節)

まあ、皆さんが一般的に思い浮かべる神様のイメージだと思ってもらっていいでしょう!
旧約聖書に登場するのは、基本的にこの創造主です。
絵画などでは老人の姿で描かれることが多いですね。
✅神様がどんなお方なのかは、以下の記事で書いています。
・【キリスト教】神とは誰か?何者か?聖書から7つの性質を挙げてみた
・ヤハウェの正体とは?名前を言ってはいけない存在?【創造主】
②子なる神(イエス・キリスト)

神でありながら人間の姿で地上に来られた救い主で、父なる神の子供にあたります。
キリスト教の象徴的存在ですね。
父なる神は私たち人間を愛するがゆえに、ご自分の独り子であるイエスを地上に送られ、十字架に架けられました。
それは私たち人間がアダムとイブの頃から背負っていた罪をゆるすためです。
「神はそのひとり子を賜わったほどに、この世を愛して下さった。それは御子を信じる者がひとりも滅びないで、永遠の命を得るためである。」
(ヨハネによる福音書3章16節)
ところが、イエスは十字架の死から3日目に復活。
弟子たちにこのことを多くの人に伝えるようにと語り、天に昇って行かれました。

✅詳しくは、【完全版】イエス・キリストとは?その生涯を簡単にまとめてみたをどうぞ
③御霊なる神(聖霊)

イエスキリストを信じた者に宿る神の霊。
イエスは自分が昇天した後に、聖霊を送ると弟子たちに約束をされていました。
「しかし、助け主、すなわち、父がわたしの名によってつかわされる聖霊は、あなたがたにすべてのことを教え、またわたしが話しておいたことを、ことごとく思い起させるであろう。」
(ヨハネによる福音書14章26節)
実際、イエスの昇天後に弟子たちに聖霊が注がれ、彼らはキリストのことを多くの人に大胆に語るようになります。
(【行事】ペンテコステとは?わかりやすくクリスチャンが解説も参照)
このように、聖霊というのは、私たち人間に語りかけたり力を与えたりしてくださる存在なんですね!

「彼がこのことを思いめぐらしていたとき、主の使が夢に現れて言った、「ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリヤを妻として迎えるがよい。その胎内に宿っているものは聖霊によるのである。 21彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名づけなさい。彼は、おのれの民をそのもろもろの罪から救う者となるからである」。」
(マタイによる福音書1章20、21節)
聖霊は、白い鳩や火の姿で描かれることが多いですね。
✅詳しくは、【神の位格】聖霊とは?その10の働き・役割をクリスチャンが解説!をどうぞ
三位一体説はどのようにして生まれた?【2つの会議で成立】
では、三位一体説というのは、どのようにして生まれたのでしょうか。
これには、主に2つの会議が関わっています。
- ニカイア公会議
- コンスタンティノープル公会議

①ニカイア公会議

318年、父なる神と子なるキリストはどのような関係にあるのかをめぐる論争が起こりました。
そこで325年にローマ皇帝のコンスタンティヌス帝が開いたのが、ニカイア公会議です。
この会議では、主に以下の2つのグループが対立することになります。
- アリウス派
➡キリストは父なる神から生まれた子であるので、父と同レベルの神の性質は持っていない。
- アタナシウス派
➡キリストは父なる神と同じ神の性質を持っている。
結果的に、この会議によって、キリストが父なる神と同じ本質を持っていること(ニカイア信条)が認められ、
アタナシウス派は正統、アリウス派は異端とされました。
ただし、この会議により“聖霊は神の性質を持っているのか”という新たなテーマが浮上してきます。

②コンスタンティノープル公会議

ニカイア公会議でニカイア信条が認められましたが、その後も論争は続き、この考え方に反対する人たちもいました。
そんな中、381年に東ローマ皇帝のテオドシウス帝が開いたのが、コンスタンティノープル公会議です。
この会議ではニカイア信条が改めて承認され、
聖霊も神の性質を持っていること(ニカイア・コンスタンティノープル信条)が認められました。

キリストも聖霊も神に造られた被造物ではなく、神そのものに等しい存在。
こうして、この信条からキリスト教の中心的な教えとなる三位一体論が生まれていくのです。
日本では昔”三位一体の改革”が行われた?
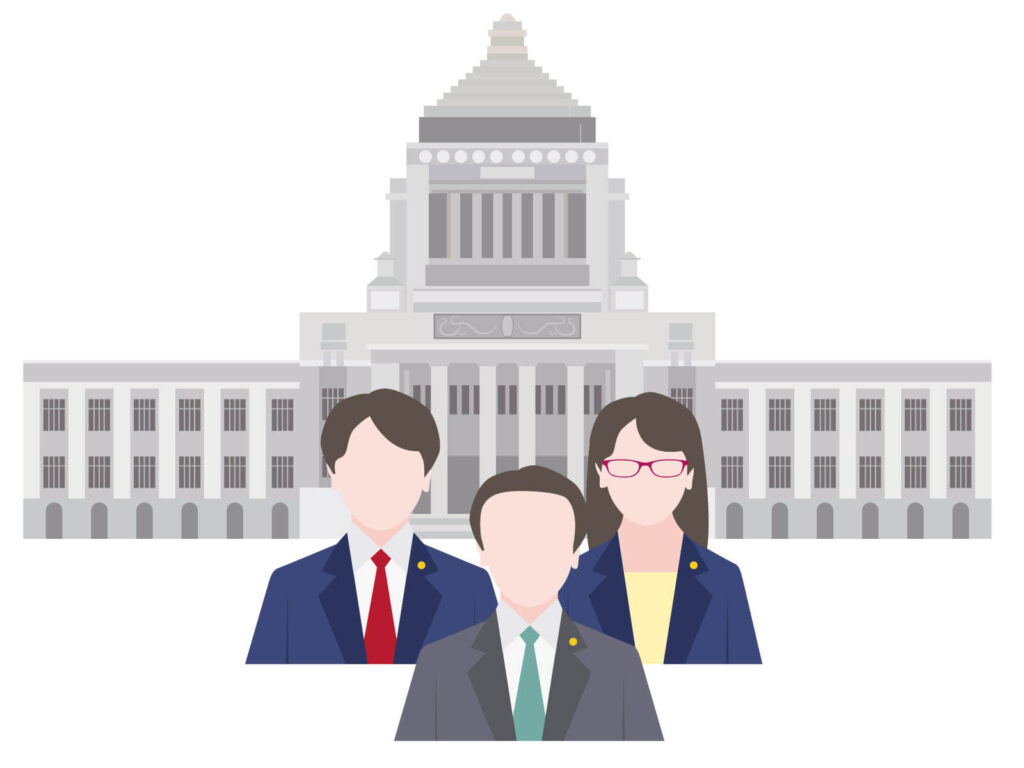
以上がキリスト教における三位一体の解説ですが、ここから派生して一般的にも三位一体という言葉が使われることがあります。
ただし、それは本来の意味ではなく、
- 3つのものが本質的に全く同じであること
- 3つのものが一つになること
というような意味で使われることが多いです。
例えば、政治において”三位一体”でいうような表現が使われることがあります。
中でも有名なのが、2002年に日本で経済財政諮問会議において示された“三位一体改革”です。
三位一体改革とは、行財政システムの3つの改革として
- 国庫補助負担金を減らすこと
- 税財源の地方への移譲
- 地方交付税の見直し
を掲げたものですね。

これら3つを1度に行うという意味で、三位一体という言葉が使われたのでしょう。
ただし、あくまでも、三位一体の語源はキリスト教にあります。
ですから、本来の意味をしっかりと押さえておきましょう!
まとめ:三位一体説を理解するのは難しい!

三位一体は、キリスト教の中でも特に難しい概念です。
なぜなら、身近に当てはまる例がなく、私たち人間の理解をはるかに超えた概念だからです。
3つのものが合体して1つになるわけでも、ただの多重人格というわけでもない。
それぞれ別の位格があるのに、それぞれが独立して別々の場所に存在することができる。
まさに、神様は私たち想像をはるかに超えたお方だということですね!
ですから、私たちがすぐに理解できなくても当然なのです。
まあ、
全ては、神のみぞ知るってことですな。(雑なまとめ)
キートンでした。


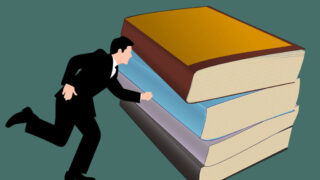
👇参考文献
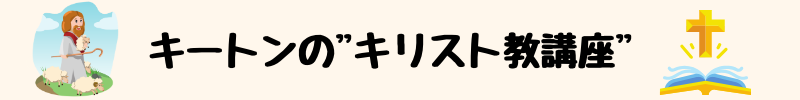


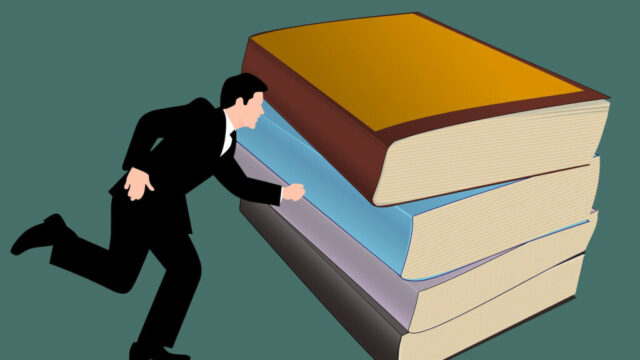






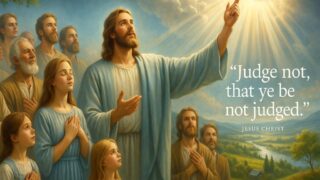


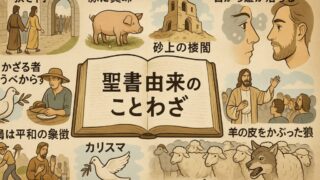
三位一体について読ませて頂きました。一人の神が3つの位格を持っているということがよく分かりません。
「子なる神キリストは神でありながら人間の姿で地上に来られた救い主」は分かりますが、「父なる神の子供にあたる」ことがわかりません。神様に人間と同じ様な親子関係があるのでしょうか。これでは父なる神と、子なる神とで神が二人になると思います。
私が昔読んだ本に書かれていた事をご紹介しますね。
ご参考になれば・・・。
”「子馬」や「子牛」は、それぞれが「馬」であり、「牛」である事が分かります。
「神の子」とか「子なる神」と言う場合も、これは人間の親子の様な関係を言っているのではなく、「神」である事を示しています。”
なので、父なる神(創造主なる神)と、子なる神(人の姿をとって地上に現れたキリスト)とは人間的な親子関係ではない。
と言う事になります。
また、創造主、イエス・キリスト、聖霊は、それぞれ役割が違うけど同時に存在していて、しかし別のものではない、つまり神が3人居る訳では無い、ので、父なる神(創造主)と、子なる神(キリスト)とえ、二人になる訳では無い、そうです。
でも、人間の脳では完全に理解出来ない事らしく、人間の思考を超えている、と良く言われますね。
それに、父なる神と子なる神に人間の親子関係の様なものは無い、と言いながら、旧約聖書でアブラハムが息子イサクを神に捧げる、と言う行為が、イエス・キリストの十字架刑の予表と言われるし、新約聖書でもイエス・キリストがバプテスマを受ける時、「これは私の愛する子」と天から声がしたり、人間の親子が持つ感情を思わせる表現が出てくるので、混乱しますね。
実際、洗礼を受けたクリスチャンは神の子供となり、神様を「天の父なる神」と呼ぶし、イエス・キリストは長子で、皆が兄弟姉妹になる、と言うので、じゃあやっぱり親子になりますね・・・。